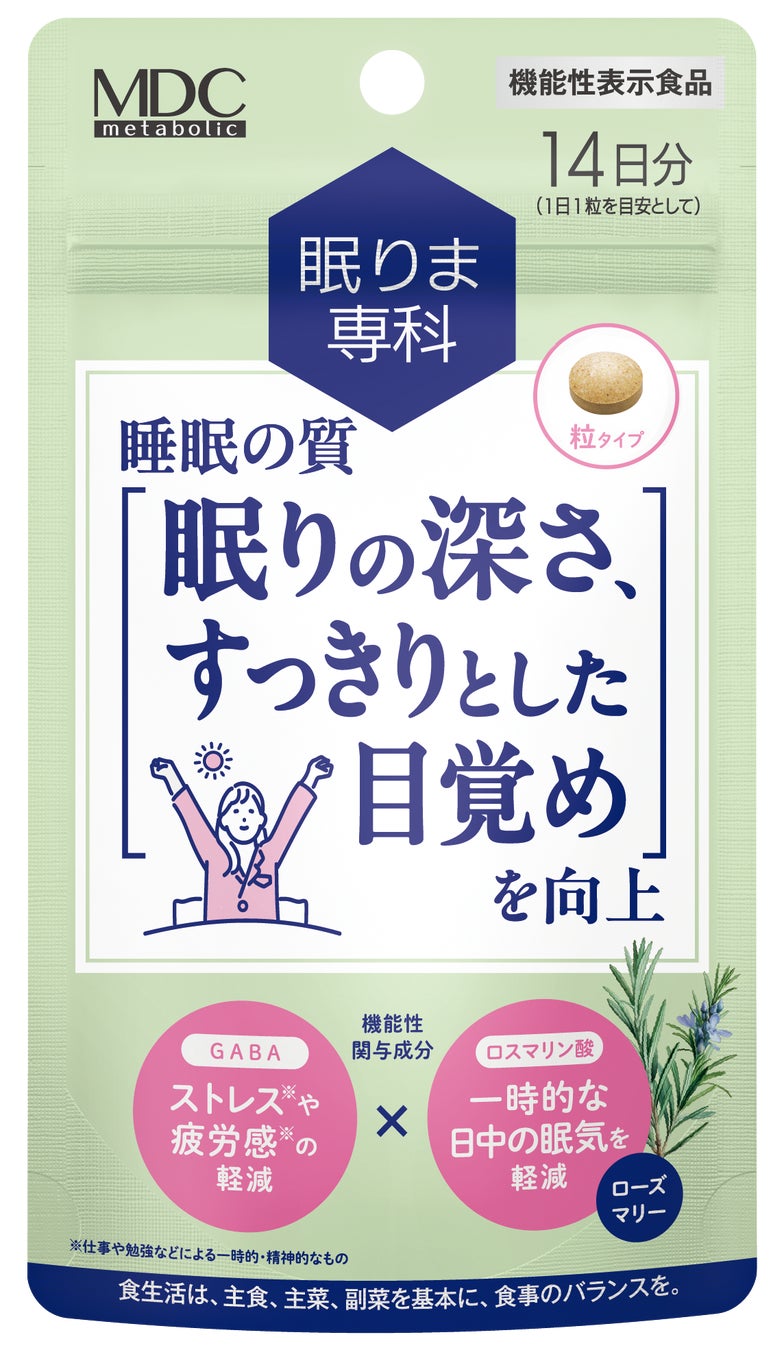「朝…なかなか起きられない」「眠ってもいまいち疲れが取れない…」そんな悩みを根本解決するにはどうしたらいい?
大正製薬株式会社のプレスリリース
3月14日は「世界睡眠デー」です。まだまだ気温の低い朝が続きますが、4月に始まる新生活にむけて、しっかりと疲労を回復し、スムーズに起床できる質の高い睡眠を習慣にしたいところです。
2025年1月に大正製薬株式会社が全国の20代以上の男女1000人を対象に「朝、すっきりと起きるために、どんな対策をしているか」を調査したところ、上位5つは、「部屋や寝具を快適な温度にする(249人)」、「規則正しい生活を送る(235人)」、「寝る直前に食べないなど、食事の時間に気を付ける(182人)」、「部屋を快適な湿度にする(159人)」、「(適度な)運動をする(144人)」、「朝起きたら朝日を浴びる(121人)」という結果になりました。

日本睡眠学会専門医で日本医師会認定産業医の白濱龍太郎先生によると、睡眠の質を上げるためには、環境づくり、生活習慣、食事などを組み合わせて対策することが重要だといいます。
白濱先生に、睡眠の質を上げる方法とその理由を伺います。
【監修】「RESM新東京 スリープメディカルケアクリニック」 院長 白濱龍太郎先生

慶應義塾大学訪問准教授。東京医科歯科大学呼吸器内科や睡眠制御学快眠センター勤務等を経て、2013年に睡眠・呼吸器科の専門医院を開設。翌年には経済産業省海外支援プログラムに参加し、インドネシア等の医師たちへ睡眠時無呼吸症候群の教育を行う。2018年、ハーバード大学公衆衛生大学院の客員研究員として睡眠に関する先端の研究に従事。日本睡眠学会専門医、日本医師会認定産業医。
日中の過ごし方で意識すべきこと
朝日を浴びると、体が活動的になります。光の刺激が脳に伝わることで、セロトニンやナイアシン、トリプトファンといったホルモンの分泌が促され、体内時計がリセットされるからです。
日光は10時頃までに浴びると効果的とされ、浴びる時間は夏場は5分程、それ以外の季節はゆったりと30分程がおすすめです。
入浴は、寝る1~2時間前までに38~40℃のぬるま湯にゆったり10分程浸かると体温を程よく上昇させることができ、寝つきが良くなります。
適切なタイミングと時間で入浴することで、入眠後、最初の90分の眠りを深くしてくれる効果があります。
また、1日10分でも運動習慣を作ることは、適度な疲労感につながります。メラトニンの材料であるセロトニンの分泌が増えることで、夜にメラトニンがしっかりと分泌されて睡眠の質の向上につながるので取り入れてみてください。ウォーキングや踏み台昇降などがおすすめです。
睡眠の質の向上に必要な栄養
朝昼晩と、食べるタイミングによって摂取したい食材が変わるので、三食の内容をそれぞれ気にしてみましょう。
夜になるとセロトニンというホルモンがメラトニンに変わり、このホルモンが眠気を起こし、スムーズな入眠につながります。夜、メラトニンがしっかり分泌されるようにするために、朝食にセロトニンの材料となる必須アミノ酸のトリプトファンを豊富に含む食品を取り入れるのがおすすめです。トリプトファンが豊富なのは、納豆やヨーグルトなどの発酵食品。他にも、幸せホルモンともいわれるセロトニンを合成するビタミンB6を含むいわしや鮭などもおすすめです。
昼食は、食後に過剰な眠気を催さないよう炭水化物はやや少なめに、血糖値が上がりにくいものを選びましょう。また、タンパク質、野菜などの食物繊維もバランスよく取り入れましょう。最初に野菜など食物繊維を摂ることで血糖値の上昇を緩やかにしてくれ、タンパク質にはトリプトファンが含まれるため、良質な睡眠を促してくれる効果が期待できます。丼ものよりも定食を選ぶと、炭水化物(ごはん)の量も調整しやすいですよ。
夜は、お酢やカプサイシン(交感神経を刺激する作用があるため激辛ではないもの)、GABA(副交感神経を優位に働かせてくれる)、タウリンなどを摂るといいでしょう。
お酢に含まれる酢酸には胃腸での消化吸収を穏やかにする作用があり、血糖値の上昇を緩やかにしてくれます。唐辛子やキムチなどに含まれるカプサイシンも、寝る前に体温を上げてくれるのでおすすめです。キムチはGABAも含む優秀食材です。
タコやイカなどの魚介類に多く含まれるタウリンは、深部体温を低下させる効果や睡眠を調整する因子(CHRM1、CHRM3)を増加させる効果があり、安定した睡眠を助けてくれる可能性があります。
魚の場合は皮や軟骨などに多く含まれるグリシンも、中枢神経系で抑制性神経伝達物質として働き、体温の調整や睡眠の質の向上に関与することが明らかになっています。魚を皮ごと食べれば、タウリンとグリシンが併せて摂れて、神経疲労、肉体疲労の両方にアプローチできますね。
適切な水分補給量とお風呂のタイミング
人は寝ている間にコップ一杯の汗をかくと言われています。
季節やコンディションによって差はありますが、寝る1時間~30分前くらいまでに200~250mlの水分補給がおすすめです。
水分を摂ることで血栓予防ができます。また、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできることで、睡眠の質を高めることができます。
このとき、利尿作用がないものや白湯など冷たくないものがおすすめです。
また、お酒には筋肉を緩ませる作用があり、寝る直前の飲酒は、いびきや無呼吸の原因になるので、避けたほうがベターです。ですが、寝るまでに数時間ある晩御飯などのタイミングで適量飲むことはリラックス効果が期待できます。
睡眠に適した環境づくり
電気毛布を使用して布団を温める場合は、就寝してから約30分〜1時間後に最初の深いノンレム睡眠が現れることも考慮して、就寝後約2時間で切れるタイマー設定が良いでしょう。
他にも、血行を良くする作用のある繊維を使ったパジャマの着用や、放熱がきちんとされるために靴下を履かないことも睡眠を助ける要素となります。
安全でスムーズな寝起きのためにできること
照明をつけることで脳が先に光を感知し、目が醒めます。ただ、寒い朝に急に暖かい布団から出ると、血管が急激に縮小してしまうことでヒートショックなどを起こすリスクもあるため、タイマーで部屋を暖めておきましょう。また、乾燥しやすい冬は湿度も併せて気にしておきましょう。部屋の温度は18~23℃、湿度は40~60%が理想的です。
照明や音も大切な要素です。照明は好みにもよりますが、豆電球の常夜灯を点けておいたり、足元を照らすダウンライトのような光量が良いでしょう。明るすぎると交感神経が有意になり、メラトニンの生成を抑えてしまうので避けましょう。
音については、無音のほうが落ち着くという人は無音でも構いませんが、むしろ無音だといろいろな音が気になってしまうという場合もありますので、心が落ち着く音楽を、ボリュームを絞って流すこともおすすめです。実際に、飛行機に乗っている時にジェット機のエンジン音が気にならないように機内BGMを導入する航空会社もあります。
睡眠不足は、日中の集中力や判断力の低下につながり、長期になると認知症のリスクが上がるとも言われています。また、睡眠は脳脊髄液の流れを促進することで脳の回復も担うため、睡眠と脳脊髄液には密接な関係があります。睡眠不足の状態だと脳脊髄液の流れが悪くなることで老廃物が蓄積しやすくなり、脳の機能や健康に悪影響を与える可能性もあります。
睡眠の質を向上させてすっきりと起きることを習慣にして、季節の変り目を健康に過ごしましょう。